6 月6日(金)主催講座4「北海道にあった擦文・オホーツク文化」の第1回「オホーツク文化―縦横無尽の海の民―」を石狩市花川北コミュニティセンターで開催しました。講師は、北海学園大学など非常勤講師の澤井 玄さん、受講者は、36 名でした。
澤井さんは「みなさん、こんにちは。私は、根室生まれで高校からは札幌に住み、東京の大学へ進みました。東京で北海道のことを聞かれても何も分からず、これではいけないと思い北海道の歴史を勉強し始めました。今回はオホーツク文化についてお話させていただきます。ただ、オホーツク文化については話すことがいっぱいありすぎてすべてをお話しするには相当な時間が要りますので、できるだけ要点をまとめてお話ししていきたいと思います」と言って講座を始められました。
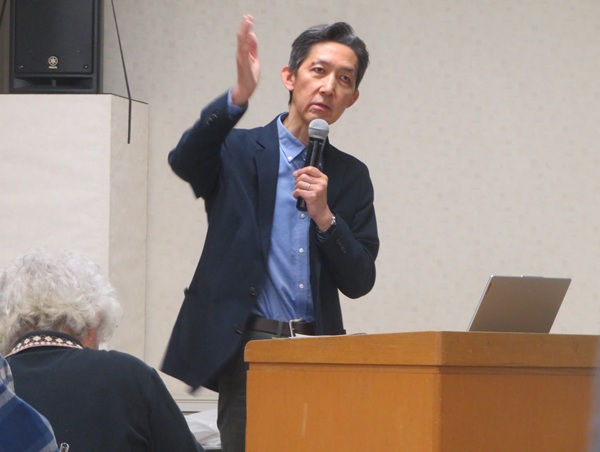
1.本州の時代区分と北海道の時代区分
◇本州
旧石器時代―縄文時代―弥生時代(稲作文化)―古墳時代―飛鳥時代―奈良時代―平安時代
◇北海道
旧石器時代―縄文時代―続縄文時代(非稲作文化)―擦文時代
オホーツク文化は、続縄文時代後半から擦文時代にかかる時期の外来文化。
2.オホーツク文化について
①環オホーツク世界
【地理的範囲】
・サハリン(樺太)~北海道~千島列島
【環オホーツクの視点】
・オホーツク海のほとりに誕生した文化
・オホーツク文化は、オホーツク海の南岸の文化
・北岸は、古コリヤーク文化・トカレフ文化
オホーツク文化は、オホーツク海の南の文化である。
【海洋適応】
オホーツク海という環境に高度に適応した生活様式を持つ文化。
②北海道の主なオホーツク文化遺跡
・利尻・礼文島、枝幸町目梨泊遺跡、網走市モヨロ貝塚、北見市常呂遺跡群、根室市弁天島遺跡、奥尻島等
③モヨロ貝塚(網走川河口)の発掘
オホーツク最大級の貝塚。米村喜男衛(大学の先生等ではなく職業は床屋さん)が 1913(大正2)年にその価値を見出した。太平洋戦争が始まる直前、海軍の施設を作る計画があり貝塚が壊されそうになったが、米村が国指定の遺跡(天皇が指定したことになる)であると抗議して、貝塚は残された。
・モヨロ貝塚館新館(2013 年に開館)
小規模だが、工夫がこらされた楽しい博物館。
④出土品
・鳥骨製針入れ(根室弁天島遺跡出土、長さ 8 ㎝、北構保男氏発掘)
漕ぎ手が6人の船に乗った狩人が描かれ、高度な狩猟・航海技術を持っていた事が分かる。
・船型木製品(羅臼町松法川北岸遺跡出土・羅臼町郷土資料館蔵)
ミニチュアの船。小さな櫂が添えられている。
・狩猟具
骨角製回転式銛
獲物に向かって投げ、突き刺さった後ラインを引くと獲物の体内で回転し、皮革に引っかかって抜けなくなる。
・豊かな動物意匠
セイウチ牙製シャチ・クマ(湧別町川西オホーツク遺跡)、熊頭注口木製槽(羅臼町松法川北岸遺跡)、木鎖状木製品(網走市モヨロ貝塚)、ヒグマの犬歯を彫り込んで製作したラッコ(北見市常呂川河口遺跡 15 号竪穴)
・歯牙製女性像 通称「オホーツクビーナス」(礼文島伝重兵衛沢出土)、巫女(シャーマン)?
⑤大陸から運ばれた宝物
船を使った広範囲な往来による様々な搬入品。大陸・アムール川流域の靺鞨文化との交易。
青銅製帯飾、軟玉製環飾、ガラス玉、カラフトブタ、イヌ、鉄製刀子、銀製装飾品、鉄鉾、曲手刀、鉄斧、穀物、金属製鐸など
・青銅製帯飾(モヨロ貝塚)⇒シャーマニズムと関連か?
⑥本州から運ばれた宝物 本州・律令国家との交易
蕨手刀、直刀、鉄斧、鉄鎌、鉄製刀子、土師器など
・金銅製直刀(2018 年発見、枝幸町教育委員会蔵)
目梨泊遺跡より出土。金銅製直刀の足金具(刀を帯から吊るすための刀装具)には全面に宝相華文(ほうそうげもん、仏教系の文様の一種)が施され、花弁の間は魚々子(ななこ、彫金技法の一種)で埋め尽くされている。木質部には漆被膜が残り、錫粉を用いた蒔絵が施されている。
この刀については、日本国内産か中国産か、まだ決着がついていない。
⑦オホーツク文化の住居
・住む場所は海辺―海に適応した文化
・平面が六角形
・広さが 100 ㎡を超える大型住居
・5~7 家族(20~30 数名?)が寝食を共にした集団生活
・遺跡は多いが住居が作られた遺跡は少ない⇒特定の定住地からいくつもの猟場に出かけて行った
・骨塚の存在―ヒグマをはじめとした魂を天に送る儀式?
モヨロ貝塚にはヒグマの頭骨が整然と積み重ねられた骨塚がある⇒獲物を祀って、豊漁・豊猟を祈願するための祭壇か?
⑧オホーツク人の墓
甕被り葬(かめかぶりそう)―手足を折り曲げ、頭部に甕を逆さに被せられて埋葬される。
⑨オホーツク人の特徴
ルーツはアムール川下流域に住むウリチ民族に近いか?
3.オホーツク文化の変容 8・9 世紀頃から
・遺跡が海から離れる⇒生業の変化⇒狩猟対象が海獣から陸獣へ
・竪穴住居が小型化⇒伝統儀礼の喪失
生業や社会に大きな変化が起きたと思われる。
4.石狩市のオホーツク文化
岡島洞窟遺跡―昭和 11 年、34 年の 2 度の発掘調査により、縄文文化期から擦文文化期までの 7 期間にわたる住居跡と判明。内部からは人骨、土器、石器などが多数出土した。特に第 4 文化層からはオホーツク土器が発見され、注目されている。
最後に澤井さんは、この方たちがいなかったら自分の研究もできなかったとして、3 人の在野の研究者とその著書、最近の一般向け書籍を紹介して本日の講座を終えられました。
網走 モヨロ貝塚 米村喜男衛(1892~1981)「モヨロ貝塚」 1969年 講談社
常呂 常呂遺跡群 大西信武(1899~1980) 「常呂遺跡の発見」1972年 講談社
根室~北千島 北構保男(1918~2020) 「古代蝦夷の研究」1993年 雄山閣
一般向けの書籍として、
米村衛「北辺の民 モヨロ貝塚」2004年 新泉社
野村崇・宇田川洋編「新・古代の北海道2 続縄文・オホーツク文化」2003年 北海道新聞社

講座は、非常に内容の濃いものでオホーツク文化のことが大変よく分かりました。受講者も大満足だったようです。
最後に受講者から寄せられたコメントをいくつかご紹介します。
「出身地が道東で、こんなにも豊かな文化があったことに驚いています。次回の講座も楽しみにしています。ありがとうございました」
「あまりよく知らなかったオホーツク文化についてのお話をうかがえてたいへん興味深かったです」
「大変楽しく学べました!ワクワクしっぱなし。オホーツク文化には特に興味があり(網走に住んでい たこともあり・・モヨロ貝塚近く)又北方民族の人々の暮らしを分かりやすく教えていただき更に詳しく学びたいと思いました」
「初めてオホーツク文化のくわしい内容を学ぶ機会に出会い、その文化の高度さに感動しました。岡島洞窟につながったのは嬉しいです。もっと知りたいです。かめかぶり葬を見ると、現代の火葬では DNAしか残らない?反省させられます。ありがとうございました」
「オホーツク文化の講座はめずらしく、よかったです」
「大変興味深く聴講させていただきました。ありがとうございました」