6月3日(火)、主催講座3「初心者のための初心者の俳句教室~俳句を楽しみ、作ってみよう~」の第3回「初心者のための俳句の実践教室」を石狩市花川北コミュニティセンターで開催しました。講師は、「石の花俳句会」代表の赤繁忠弘さん、受講者は21名でした。
赤繁さんは「みなさんこんにちは、これまでと変わらぬお顔を拝見して嬉しく思います。最初にひとつお聞きしたいことがあります。みなさんはこれで3回目の講座になりますが、これからも俳句をやっていきたいと思っていらっしゃる方はどのくらいいらっしゃいますか?」と尋ねられました。手を挙げた方は数人。「あれっ、全員が手を挙げられるかと思っていましたが」と赤繁さん。
「今日は、みなさんに俳句をおひとり一句作っていただきます。どのような形でやっていただくのが良いか色々考えました。前もって題を出すのが兼題、その場で題を決めるのが席題ですが、今回は席題にしたいと思います。席題の自由句にします。自分が思った句を一句作って下さい。実は、今日は暑いので、席題を扇風機にしようか、ところてんにしようかと考えたのですが、題を決めると初心者には厳しいと思い直して、自由句にしました。題を決めると評価はしやすいのですが、ちょっと難しくなってしまいますので自由句にします。17文字で季語をひとつ入れて下さい。
句を書く紙もマジックも用意してありますので、句を書いたら前に持ってきて下さい。それをホワイトボードに貼ります。そして皆さんに見ていただきます。見て、自分が一番良いという句の番号を覚えておいて下さい。最後にこの句はどうですか、と聞きますので良いと思うものに手を挙げて下さい。
手順はこんな感じです。添削も今日はあまりしないつもりですが、直して良くなる場合は直したいと思います。これから30分で作ってもらいますが、質問があればどんどん声をかけて下さい」

いよいよ俳句つくりに挑戦です。
結果は、なかなか立派な19句が集まりました。

みなさんホワイトボードの前に集まり、どの句が良いか色々考えてみました。

「石の花俳句会」の紹介もありました。
■句の講評
19句のうち、3人が良いと手を挙げた句が1句。2人が手を挙げた句が2句ありました。
◇3人が良いと手を挙げた句
「わしゃ白寿おまえ卒寿で昭和の日」
◇2人が良いと手を挙げた句
「風鈴の音色やさしく夢の中」
「汗にじむ畑耕す母の背や」
「若草の匂いあふるる防風林」
◇添削すると良くなる句
「汗にじむ畑耕す母の背や」この句は、汗(夏)と耕す(春)の二つの季語が入っている。
添削⇒「母の背や畑耕す鍬の音」
「五月雨に植えたトマトも生き生きと」⇒「五月雨に植えたトマトは生き生きと」
「は」を使って間をつくる。助詞の使い方は大事。助詞を大事にしないと句作は上達しない。
「あき家や猫がねそべり陽だまりに」季語がない⇒「あき家に猫がねそべる昼寝かな」
「パンよりも米恋しいが手が出ない」⇒「パンよりも手が出せないよ今年米」
「星月夜アイエスエスが花を添え」星月夜(秋)と花(春)の季語が二つ⇒「星月夜アイエスエスが未来へと」※アイエスエスは、国際宇宙ステーションのこと。
◇赤繁さんに直しなどいらないと言われた句
「村カフェのきび糖プリン風薫る」
「うとうととバス乗り越して秋の宵」
「わしゃ白寿おまえ卒寿で昭和の日」
赤繁さんは「みなさんが今日作られたような句で大丈夫です。作り続けて下さい。前回もお話ししましたように、作り続けていくと壁にぶつかります。そういう時にはどうしたらよいか、ぜひ私どもの句会を訪ねてください」と話され「この3週、いろんなお話をしましたが、まだまだお話ししたいことがいっぱいあります。それはまた何かの機会にみなさんにお会いすることがあればお話しできますし、私どもを訪ねていただいてもお伝えできると思います。私の話を3週にわたり聴いていただきましてありがとうございました」と言って講座を締められました。
最後に全員で記念写真を撮って解散しましたが、3回の講座は大変充実したもので、講座の内容にも自分が作った句にもみなさん充分納得して帰られました。
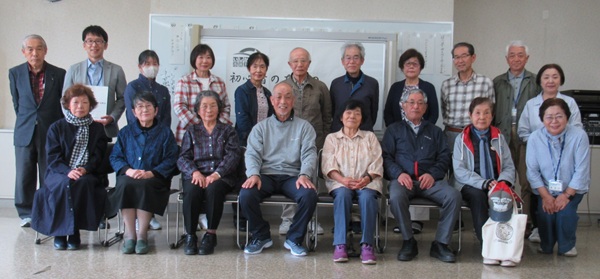
終わりに受講者から寄せられたコメントをご紹介します。
「俳句の基本、スタートの一歩でした。とても楽しく学べました。句会の重要性を感じています。やや悩みつつ」
「実際俳句を作ってみなさんで感想を言い合ったのが良かったです」
「初めて受講したが陽気な先生でとても分かりやすかった。俳句を作る楽しさを覚えることができた。季語の使い方が上達のコツか!」
「自我自尊では俳句はダメだと納得しました。これを機会に今後とも俳句に触れていきたいと思います。熱い講座、どうもありがとうございました」
「何時も家にいてばかりで、久しぶりに人の中に入らせていただきました。赤繁先生の講義も素晴らしく大正解でした(参加して)。ありがとうございました」
「講師の先生、ありがとうございました。老いに負けず死ぬまで俳句を趣味として生きたいと思います」