7月23日(水)、主催講座7「太平洋戦争、日本降伏を巡る米ソの暗闘」の第3回「ソ連の北海道北半分の占領要求と米国の拒絶」を石狩市花川北コミュニティセンターで開催しました。講師は、北海道史研究家でノンフィクション作家の森山 祐吾さん、受講者は44名でした。
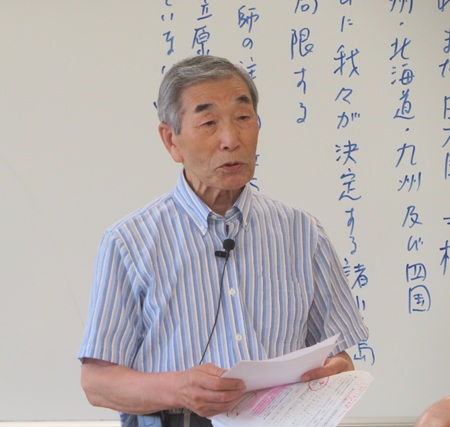
講師は最初に、2回目の講座のアンケートで寄せられた質問に一つひとつ丁寧に答えられてから、本日の講座を始められました。
3回目のお話は、2回目の最後の項目の「9.終戦をめぐる米ソの駆け引きとソ連軍の侵攻」を引き継いで、「10」から始まりました。
以下はそのお話の要約です。
10.ソ連の北海道北半分の占領要求と米国の拒絶
◇マッカーサーが伝達した日本軍降伏の細目(一般命令第1号・第1項)を見たスターリンは、対日軍事作戦の即時中止と、日本軍がソ連軍に降伏する地域の範囲についてクリール(千島)列島が含まれていないことに激しい反発を見せ、マッカーサーの戦闘停止命令を無視し、一方的に戦闘を継続した。
・アントノフは、「その作戦地域内において攻撃作戦を中止するか否かは、ソ連最高司令官の判断による」としたが、最高司令官とはスターリンを指し、ソ連軍はマッカーサーの従軍部隊でないとする見解を表している。実際の軍事行動も連合軍の指示命令に従ったものではなかった。ここは、日本人にとって忘れてはならない重要な部分である。
・ワシレフスキー元帥は次のように述べている。
「8月14日(日本は15日)、天皇の行った日本の降伏についての発表は、一般的な無条件降伏に過ぎず、軍隊に対する戦闘行動停止命令はまだ出ていないので、日本軍の実際の降伏はまだない。天皇が、その軍隊に戦闘行動を停止し、武器を置くよう命令し、その命令が行われて初めて日本軍の降伏とみなすことが出来る。故に、極東ソ連軍は攻撃を続行するのである」
・事実、ソ連は攻撃を止めなかった。ソ連軍統帥部は、8月15日中に樺太西海岸の真岡及び千島進攻作戦を決定、夜半には南樺太の恵須取に向け艦船が出動した。日本政府が全軍に停戦命令を出したのは16日である。
◇スターリンは16日、トルーマンに、日本にとって極めて重要な問題を含む親展秘密電報を送った。
「命令の内容には概ね異存はありませんが、『一般命令第1号』に次の修正を加えることを提案します。
①ソ連軍に対する日本国軍隊の降伏地域に千島列島の全部を含めること。千島列島は、クリミアの3大国の決定(ヤルタ会談)によれば、ソビエト同盟の領有へ帰属すべきものである。
②ソ連軍に対する日本国軍隊の降伏地域に、樺太と北海道の間にある宗谷海峡と北方で接している北海道の北半を含めること。北海道の北半と南半の境界線は、島の東岸にある釧路から島の西岸にある留萌に至る線を通るものとし、両都市は線の北側に含めること。
この第2項の提案は、ロシアの世論にとって特別の意義を持っている。1918年~1922年、日本軍のシベリア出兵(英米伊日の連合軍が、ロシア革命によって囚われたチェコ軍団を救出する、という目的で出兵。実際はロシア革命政権の打倒を意図した干渉戦争。日本兵力7万3千人、戦費5~9億円といわれる)では全ソビエト極東を軍隊の占領下に置いていた。もしロシア軍が、日本本土のいずれかの部分に(日本軍がしたように)占領地域を持たないならば、ロシアの世論は大いに憤慨する。私は、以上に述べた私の控えめな希望が反対を受けることがないよう、切に望む」
◇スターリンは、日本降伏を目前にして、このままでは米国に仕切られて何も手にすることが出来なくなると焦り、控え目どころか、露骨に領土獲得の本音を現した。
・電報の第1項で、「クリミアでの3大国の決定」に公然と言及しているのは、重要な政治的意味を持つ。終戦から半年前の2月に、ヤルタで開かれた米英ソの3国首脳会談の際、スターリンはルーズベルトの強い対日参戦要請を受け入れ、独ソ戦終了後の3ヵ月以内に参加することを密約した。アメリカはその代償として極東におけるさまざまな権益の供与を約束した。その一つが南樺太と千島列島のソ連への引き渡しであった。スターリンは、この約束を確実に履行するように迫ったのである。
・第2項の北海道北半分の占領は、これまで参戦条件として全く持ち出していなかった追加要求である。
・マッカーサーの司令部にソ連代表として赴任していたテレビヤンコ中将は、連合軍の対日理事会で、スターリンの訓令によりクリールと北海道の北半分を占領させて、日本を2つに分けろと強く要求した。
・これについてマッカーサーは、自身の「大戦回顧録」の中でこう書いている。「ソ連軍は、マッカーサー最高司令官の指揮下に置かず、完全に切り離すべきだと言うのを私は正面から拒否したが、同中将はののしらんばかりの調子で『ソ連は必ず私(注 マッカーサー)を最高司令官の職から罷免させてみせる』と脅し、私が承知しなくても『ソ連軍はとにかく日本に進駐する』とまで断言した。そこで私は、もしソ連兵が一兵たちとも私の許可なく日本に侵入したら、テレビヤンコ中将を含めソ連代表部の全員を、一人残らず即座に投獄すると言ってやった」と書いているように、激しい攻防のすえ、ソ連の要求を拒否したのである。
◇2日後の18日、トルーマンはスターリンへ極めて重要な返電を送った。
「『一般命令第1号』を修正して千島列島全部をソ連極東総司令官に降伏すべき地域に含めるというあなたの要請に同意する。(中略)北海道島の日本武装兵力がソ連武装兵力に降伏することに関するあなたの提案は、私は日本のすべての島、即ち北海道、本州、四国、九州にある日本武装兵力は、マッカーサー将軍に降伏するものと考えていますし、これに関しては措置がとられています。マッカーサー将軍は、象徴的な連合国武装兵力を利用するでしょうが、これらの武装兵力は、連合国側の降伏条件を実行する上に、占領の必要があると彼が考える日本本土の部分を一時的に占領するためには、もちろんソ連武装兵力をも含むでしょう」
・トルーマンはこの返電で、スターリンの異議を認め、一般命令第1号を修正し、千島列島全体を日本軍がソ連司令官に降伏する地域に加えた。しかし、北海道の分割占領というソ連の提案には、きっぱりと反対し、これらの地域の降伏受領はすべてマッカーサーが行うとする米国政府の既定方針を強調している。そして、マッカーサ―が米国占領軍の司令官としてではなく、連合軍最高司令官として日本に降伏の諸条項を実行させるため、一時的に日本本土を占領するに過ぎないこともさりげなく指摘している。
◇この数日間に交わされた多数の電文のうち、もっとも注目しなければならないのは、16日付スターリンの修正提案(ソ同盟外務省編『米ソ秘密外交書簡・米ソ編』整理番号363)と、18日付トルーマンの修正同意(同番号364)の返電である。この2電は日本の北方領土に関して最も重要な正式記録であり、我々日本人が決して見逃しのできないきわめて重要な秘密電報である。
◇スターリンは、トルーマンの拒絶書簡を18日に受け取ったものの、しばらく返事を出さず、極東ソ連軍への攻撃中止命令も出さなかった。それは、米国が狡猾的でこのままではヤルタ協定(南樺太と千島列島のソ連帰属の密約)が履行されないのではないかという疑念と、日本の降伏調印後に軍事行動を強行すれば、連合国から相当の非難を受けるのは必至であるから、日本の降伏前に極力急いで占領地域を拡張し、何としても既成事実化しようとする判断があったからだと思われる。
◇スターリンがトルーマンに返事を出すのを逡巡している間にも、ソ連軍の攻撃は止まらず続いた。樺太北部の各地では、8月17日の大平病院看護婦6名の劇薬服毒死など,民邦人の悲劇が相次いだ。20日にはソ連軍は、樺太真岡町に艦砲射撃を行った後に上陸。住民が避難した後も同町に残留し、職場を守っていた郵便局交換手の女性12人のうち9人が青酸カリにより集団自決した。
・翌日、約3600人の緊急避難民を乗せた小笠原丸、第2新興丸、泰東丸は、樺太の大泊港から出港し小樽港に向かったが、22日午前4時半から正午までに、途中の増毛沖や鬼鹿沖で3隻が相次いでソ連潜水艦に攻撃され、小笠原丸と泰東丸は沈没、第2新興丸は大破しながらも辛うじて留萌港に到着した。3隻で約1700人が死亡する大惨事が発生した。ソ連軍はこれを戦争中の当然の出来事として意に介さず、この事件は1992(平成4)年9月まで極秘にされた。南樺太の約41万余人の日本人のうち、この2週間で死者は4400人に達し、うち民間人3700人が犠牲になった。
◇本気で北海道占領を計画したスターリンは、トルーマンに修正案を送ると同時に、極東総ソ連最高司令官ワシレフスキーに対し、9月1日までに、釧路から留萌を結ぶ北半分の北海道島と南クリール(択捉、国後)を占領する命令を出した。
・これに基づき、直ちに歩兵2個師団、戦闘機及び爆撃機は各1個師団の計の4個師団と太平洋艦隊の一部を北海道に投入する計画が策定された。
・ワシレフスキーは、22日午前、南樺太の極東第87歩兵軍団に対して、北海道上陸作戦遂行のため、船舶への乗船と諸機材の積み込み態勢を急ぎ整えるよう命令した。続いて同日午後3時過ぎ、第1、第2極東戦線司令官、太平洋艦隊司令官、極東空軍司令官に対し、「明23日夜から北海道上陸作戦を開始する。直ちに準備に入れ。但し、この作戦はモスクワ本部の特別指令によってのみ開始すべし」と厳命した。
◇ところが同日夜遅く、スターリンは理由も告げず、突如北海道上陸作戦の中止命令を出し、各部隊に千島占領作戦の支援に加わるよう変更指示を下した。スターリンが、同日のうちに攻撃準備と中止という最も重要な極秘指令を発したことは、緊迫した中でギリギリの決断を迫られたスターリンの心中を示すものである。
・北海道上陸を断念した理由は、日本軍の第91師団千島守備隊8500人がソ連軍に頑強に抵抗したことと、南樺太東岸においても日本の第88師団2万人の懸命な抗戦で、ソ連は北海道占領作戦準備基地となる樺太南部大泊の占領が遅れ、上陸作戦開始予定の23日夜までに占領が完了できない情勢となったためである(※占領は25日になった)。
・このままでは日本の降伏調印前に、北海道どころか千島の占領も既成事実化できないと判断したスターリンは、最大の狙いである千島列島の占領作戦を優先せざるを得ない状況に立たされた。さすがのスターリンも、これでは北海道上陸は無理と見て、8月22日中に再びトルーマンに電報を送った。
◇「貴下の書簡の内容を、私は、ソ連軍に対する日本武装兵力の降伏地域に、北海道の北半を含めてくれというソビエト同盟の要請を、叶えることが拒否されている意味において理解しました。しかし、私と我が同僚たちは、貴下からこのような返事を受け取るとは予想もしていませんでした」と皮肉たっぷりに述べている。スターリンは、北海道の北半占領が、米国の強い反対を招いたことと、戦後の対米関係を対立状態からはじめることを望まなかったからと思われる。
◇こうして、ソ連の北海道分割要求は、樺太、千島の日本軍の善戦とトルーマン、マッカーサーの断固たる態度で拒否され、スターリンの北海道上陸作戦は決行寸前で「幻の計画」に終わり、北海道分割の悲劇は危うい処で回避された。
◇しかし15日の終戦から22日の中止命令までのわずか1週間の間に、北海道をめぐる米ソの激しい攻防が繰り返される中でもソ連の侵攻は続き、さらに日本は南樺太の知取までと千島列島北端の占守島を失ってしまった。
・日本軍は25日に作戦任務を解除し、武器の引き渡しを行ったのは、樺太では27日、千島方面では31日であった。
・ところが、日本の正式降伏調印が日本側の都合と、台風の本土接近による受け入れ準備の遅延によって、当初のマッカーサー司令部の予定より5日間延期されて9月2日となってしまった。
・スターリンはこれを最期のチャンスと見てなおも貪欲に領土奪取を続けた。
・この1週間のズレによって、ソ連軍は9月1日までに南樺太の残る領土全部と千島の北部・中部及び南部の北方領土4島に上陸攻撃を継続し、後にこれらの占領地はソ連領土として事後承認されてしまったのである。
・しかも歯舞諸島の占領は、日本の正式降伏調印後の9月5日に行われたが、これは完全な命令違反である。
◇この時、米軍が進攻してくると思っていた北方領土島民は、思いもよらないソ連軍の突然の上陸と、ソ連赤軍司令官の日本軍の武装解除などで、大混乱に陥った。瞬時に占領され、残された島民の恐怖感や危機意識は相当なものであった。
・31日、択捉島留別村長から根室支庁長あての電報は「言語通ぜず至急通訳派遣せられたし」とあり、これに対して「当地には通訳居住せず。なお、船舶航行禁止の状態なり、ご配慮を乞う」という何ら対応が出来ない苦衷の返電であった。
・9月20日、国後島留夜別村長から根室支庁長あての電報は、「現在においても国後島は北海道の一部なりや、上陸後、刻々不安の状態にいる島民の引き上げその他措置に関し、ご方針折り返し返電あれ」とあり、不安感に満ちたものである。対して同支庁長は、「国後島は北海道の一部なり。婦女子に対して引き上げ可能なるにおいては、引揚しむるを安全とするも交通禁止の現状にては、引揚げ困難ならずや。可能なら引揚げしめよ。離島の事情は道庁を通じ、詳細を中央に報告し、善処を要求しつつあり。島民協力一致し、暫くの間健闘を祈る」と返電した。
・しかし、健闘を祈るだけで何ら救済策がない返電に、危機感を募らせた島民は漁船に乗り、暗闇にまぎれて脱出せざるを得なかった。
◇こうしてソ連は、参戦の8月9日から9月1日(正確には9月5日)までの24日間という極めて短期間の軍事作戦によって、極東における戦後処理に関して絶大な利益を得た。それは、領土の占領のみならず、60万人を超える日本軍捕虜を含むものであった。
・日本の降伏を尻目に、ソ連が継続強行した対日軍事攻撃は、ヤルタとポツダムでの米ソ間の政治的取り決めを、何としてでも実施させるためのスターリンの決意を反映したものであった。
・言ってみれば原爆の登場がもたらした米ソ間の急変が、このように異常な終戦状況を生み、日本はそのツケを払わされたと言えるのではないか。
◇太平洋戦争終戦前後に、これほど緊迫した米ソの駆け引きがあったことは、今日でも一般にほとんど知られていない。歴史に「もしも」はないが、ソ連が作戦計画通り北海道北半分に進駐していたなら、すぐに撤収することなく、北半分どころか北海道全部がソ連軍に占領され、朝鮮、ドイツのように分断国家と化して悲劇に立たされていたことであろう。
11.日本の降伏と米ソ首脳の戦勝演説
◇1945(昭和20)年9月2日(日)午前9時25分(ワシントン時間は9月1日午後10時25分)、東京湾に浮かぶ4万5千トンの米国戦艦ミズリー号艦上において、日本政府全権重光葵外務大臣、日本軍(大本営)全権梅津美冶郎参謀総長と連合国最高司令官マッカーサーとの間で、日本の連合国に対する降伏調印が行われた。
・マッカーサーが、勝者と敗者の宥和の必要性を強調する感動的なスピーチを行った後、この署名式を中継したアメリカの放送局は、ホワイトハウスの大統領トルーマンの戦勝演説を放送した(要約、一部抜粋)。
◇「米国人に告ぐ。すべての米国の、またすべての文明世界の思いと希望は、今夜戦艦ミズリー号に集中した。東京湾に投錨したこの米国の領土の小さな一角でたった今、日本人は公式に武器を置いた。彼らは無条件降伏の条項に署名した。・・・4年前にはすべての文明世界の思いと恐怖は、アメリカの一部であるほかの土地、すなわち真珠湾に集中していた。我々は真珠湾を忘れないであろう」無条件降伏は真珠湾攻撃への報復であることを明らかにし、続けて最後にこう結んだ。
「米国合衆国の大統領として、私は、1945年9月2日の日曜日を、日本が正式に降伏した日、即ちVJDayと宣言する。これは米国がもう一つの日(※真珠湾攻撃の日)を恥辱の日として覚えているように、この日を報復の日として思い出すであろう」
◇戦勝演説を行ったのはもう一人いた。この調印を確認したモスクワのソビエト連邦書記長スターリンは、翌3日、ソ連国民に対する長文の戦勝メッセージを「プラウダ」紙上に発表し、対日戦争の総括を行った(以下、要点を抜粋)。
「日本の侵略は我々の連合国である中国、米国、英国に損害を与えたのみではない。それは我々に大きな損害をもたらした。したがって、我々は日本に対して我々の恨みの代償を支払わせなければならない」「よく知られているように、1904年2月、日本とロシアがまだ交渉している時に、日本はツアーリスト政府の弱みにつけ込んで、突然に裏切って、宣戦布告なしに我が国を攻撃した(日露戦争のこと)」
◇スターリンが言おうとしていることは、過去にロシアがいかに日本の侵略によって被害を受けたかをソ連市民に想起させるとともに、ソ連が日本を攻撃したことの正当化であった。さらに日本が宣戦布告なしに日露戦争を開始したことを、真珠湾攻撃になぞらえて、これが日本の通常のやり方であると言おうとし、逆に言えば、ソ連は日本と異なり、満州に攻め入る前に宣戦布告したことをほのめかしている。
・この箇所は明らかに中立条約に違反して対日戦争に参戦したことを正当化するために書かれたものである。
・スターリンは参戦の理由については中立条約にも、ヤルタ協定にも、またポツダム宣言にも言及せず、お茶を濁したのである。
◇しかしこのメッセージには本音と嘘が混じっているので、そのまま受け止めることは出来ない。
・日本は、1894(明治27)年に勃発した日清戦争により、清国から得た満州の権益に対して、露、独、仏の三国干渉により遼東半島を返還せざるを得なかった。その後ロシアは、満州の権益独占、シベリア鉄道の建設、旅順要塞などの軍備強化をして居座り、駐兵に加えて、日本が最前線勢力圏とみなす朝鮮半島にまで進出したので、1904年2月10日、ロシアに宣戦布告して戦ったのであり、ロシアに対する侵略とは言い難い。
◇日露戦争の結果についても触れている。
「日本の侵略行為は、1904(明治37)年から始まっていた。周知のとおりロシアは日本との戦争において敗北した。日本は、ロシアより南樺太を裂き取り、千島列島に地歩を確立し、かくて東方において我が国の太平洋へのあらゆる出路を封じた」
・ここで、スターリンは歴史的事実を歪曲している。南樺太は、確かに日露戦争後の講和条約で割譲されたものであるが、千島列島は日露戦争とは無関係である。千島列島は、日露戦争の29年前の1875(明治8)年に、通常の外交交渉を通じ、日露両国間の「樺太・千島交換条約」によって日本領土となったものであり、カイロ宣言での「暴力と貪欲」によって獲得した領土にはあてはまらない。従って、千島列島は、ソ連に帰ったのではなく、ソ連が日本から奪ったという方が正確である。
・スターリンは、ソ連国民と世界の世論に向けて、日本の固有領土の一角を占領することを正当化するためには、歴史の歪曲が必要であったのである。
◇「日露戦争の敗北は、国民の中に悲痛な記憶と、我が国に汚点を残した。我が国民は、日本が撃破され、汚点が拭い去られる日の到来を信じて待っていた。40年もの長い間、我らの古き世代の人々はその日を待った。遂にその日が到来した」
・この箇所は、日露戦争と真珠湾を取り替えてみると、スターリンとトルーマンの演説がまったく似通っていることに気づく。ロシアの敗戦は国家の恥辱であり、いつかは失地回復を成し遂げたいとする悲願を持ち続けていたことを示し、また日露戦争以来の積年の報復を今ここに成し遂げた、という復讐思想を明確に表現したものである。
・スターリンを太平洋戦争の対日参戦に駆り立てた根底には、この民族主義的な復讐思想があった。
◇続いてスターリンは、この演説の中でもっとも重要なことを述べている。
「南樺太と千島とがソ連邦に帰り、今後両地域が太平洋よりソ連を乖離することなく、また、我が極東に対する日本の攻撃基地となることなく、ソ連邦の太平洋に至る直接連絡路となり、日本の侵略に対する我が国の防衛基地となることを意味する」
・ここでは、極東での軍事作戦の動機の説明と、地政学的利益を追求している。すなわち南樺太と千島の奪回は、念願の太平洋への自由な出入り口を確保し、同時に安全保障上の価値を高めることにつながるわけで、対日参戦の戦略上の理由はここにあったのである。
◇スターリンの演説は、日ソ中立条約の違反、千島列島の占領、日本に対する戦争を正当化するうえできわめて巧みに構築されていた。この演説の中に示された考え方が、ソ連政府とソ連の歴史学者が対日戦争を解釈する基礎となっている。
◇ソ連が対外拡張を目指し始めたのは、1929年の北部満州においててあり、東欧では1939年のバルト海及び東欧の各地において、多くの領土の占領を繰り返した。欧州で十分拡張した後、矛先を極東に向けようとしていた。
・その頃(1940年時点)の南樺太と千島列島の日本にとっての位置づけは、南樺太は人口41万余人、水産、林業の豊富な資源に加え日本本土需要の20%の紙パルプと6%の石炭供給地で、北方の重要な拠点であった。一方、千島列島は人口1万7千人、漁業資源を中心とする経済価値も少なくはなかったが、同列島は北太平洋における渡り廊下のような地理的位置で、むしろ戦略的価値の方が高かった。もしソ連が対日戦に加われば、同列島を要求して、オホーツク海の支配と日本本土に対する北からの戦略的態勢を確立することが予想された。
12.日本捕虜50万人を移送せよ
◇スターリンは、終戦翌日の8月16日、捕虜のソ連領への移送は行わないと指示していた。
・しかし、1週間後の8月23日、日本軍捕虜に関する極秘指令文書(極秘命令第98号)が発行されていたことが、戦後47年を経た1992(平成4)年に明らかになった。
・この指令書は、シベリア抑留の原点を証明する貴重な資料である。
◇スターリン政権は、日本の敗北が近いと判断し、樺太、千島列島への進攻の頃からすでに捕虜獲得計画を周到に練り上げていたことを裏付けている。
・同指令文書は、冒頭で「国家防衛委員会決定 1945年8月23日 モスクワ、クレムリン 日本軍捕虜50万人の受け入れと配置及び労働への利用について」と記載され、満州と朝鮮で赤軍が捕らえたすべての日本軍捕虜をソ連に送るよう命じている。
・ソ連本土に抑留された日本軍将兵らの総数は、戦後に公式発表された厚生省援護局の資料によると57万5千人、ソ連側のシベリア抑留史研究者キリチエンコは63万9千余人と報告していることから、ソ連軍による現場での捕虜連行は、スターリン指令をはるかに上回る規模で行われたことになる。
・捕虜となった日本軍将兵は、「自国の所有物、消耗品」として扱われ、終戦後のソ連の国民経済復興のための労働力として酷使された。
・そして、日本軍捕虜が全員帰還する1956(昭和31)年まで、劣悪な環境下に抑留、労役させられ、6万人近い犠牲者を生んだ。
◇指令書の内容は、スターリンが議長を務める「国家防衛委員会」が、秘密警察のベリヤ長官と捕虜護送局長クリベンコに対し、パム鉄道(第2シベリア鉄道)建設をはじめとする木材の調達、鉱山・石炭の採掘など、作業地域・現場別に投入する捕虜将兵の人数、移送・収容条件などを詳細に指示したものである。
・日本軍捕虜の受け入れについては、「第1、第2極東戦線、バイカル戦線の各軍事評議会に対し、①シベリア、極東の環境下での労働に適した肉体条件を備えた者の中から、50万人以内の捕虜を選別し、②ソ連領への移送に先立って各1千人の建設大隊を組織し、下級士官、下士官の捕虜に、大隊、中隊の指揮を執らせる」などと命じている。
◇収容先現場は、ソベリア、ハバロフスク、クラスノヤルスク地方など12地域にわたり、計47ヵ所の強制労働現場を列挙、投入捕虜数を細かに指示している。
・一方、民間邦人については、ソ連参戦当時、満州方面だけでも155万人の一般在留邦人がいたが、引き揚げまでに約18万人が死亡、特に満州開拓民24万人は3分の1の8万人が命を落とし、数千人の子供が「戦災孤児」として大陸に残された。
◇日本軍将兵の大量捕虜抑留の問題は、北海道占領の断念の代償であり、スターリンの野望というより復讐によって生み出されたものであったといえよう。それは同時に戦争終結の直前、日本領土の奪取と戦後の覇権をめぐって、米ソの面子を賭けた激しいつばぜりあいの結果が招いた悲劇でもあった。
13.サンフランシスコ講和条約と関連事項
■重要条文・ソ連は調印しなかった
◇1951(昭和26)年9月8日、サンフランシスコ講和会議が開催された。日本は、米英を含む自由主義諸国(49ヵ国)との間に対日平和(講和)条約を締結した。
・しかしスターリンは講和会議に欠席し、代表としてグロムイコ外相を出席させた。会議の中で彼は、第2条の中に「諸島に対する完全なる主権を認め、これらの領土に対するすべての権利」という文言を加えることを強く提案したが、この修正案は他の連合国から極東で新しく戦争を準備するものであるとして否決されてしまった。
・このため彼はこれを不服としてサンフランシスコ講和条約の調印を拒否してしまった。そこにはすでにアジアにおける冷戦の激化と北方領土問題の存在があったからである。
◇この条約で日本は、朝鮮、台湾、樺太、千島列島に関する請求権を放棄した。
・北方領土に関する部分(第2章第2条・C)は次のようになっている。
「日本国は、クリール諸島(千島列島)並びに日本国が1905年9月5日のポーツマス条約(日露戦争)の結果として、主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権限及び請求権を放棄する」
◇しかし、樺太、千島列島に関して問題点は2つある。
①日本は請求権を放棄したが、これらの帰属先は明示されていない。
②千島列島の範囲が明確でない。
請求権を放棄した帰属先が、明文化がないまま条約調印国でない国(ソ連)にいくことが妥当であるのか。
・英文のクリール諸島と日本でいう千島列島は同じものであるのか。少なくとも歯舞諸島と色丹島はクリール諸島でも千島列島でもなく、地形的に北海道に付属する島々である。国後島と択捉島は、かってのロシアから奪ったものではなく、日本固有の領土である。千島列島は、条約でいうクリール諸島と同一ではないと考えられるからである。
■講和会議における吉田茂全権の「国後、択捉留保」発言
◇講和会議で日本の吉田茂全権(首相)は、「国後、択捉」について「日本の固有の領土である」という留保発言をした。これは調印前日(7日)の第8回総会で行われたもので、これに対して出席各国からは、何らの異議も質問もなかった。
・「この条約は、公正にして史上かって見ざる寛大なるものであります。従って、日本のおかれている地位を充分承知しておりますが、敢えて数点につき、全権各位の注意を喚起せざるを得ないのは、我が国民に対する私の責務と存ずるからであります(中略)。
千島列島及び南樺太の地域は、日本が侵略によって奪取したものだとのソ連全権の主張は承服いたしかねます。
日本開国の当時、千島南部の2島、択捉、国後の両島が日本領であることについては、帝政ロシアもなんらの異議を挟まなかったのであります。
ただ、得撫島以北の北千島諸島と樺太南部は、当時日露両国人の混在の地でありました。1875(明治8)年5月7日、日露両政府は、平和的な外交交渉を通じて樺太南部は露領とし、その代償として北千島諸島は日本領とすることに話し合いをつけたのであります。
その後樺太南部は、1905(明治38)年9月5日、ルーズベルト大統領の仲介によって結ばれたポーツマス平和条約で日本領になったのであります。
千島列島及び樺太南部は、日本降伏直後の1945年9月2日、一方的にソ連領に収容されたのであります。また、日本の本土たる北海道の一部を構成する色丹島及び歯舞諸島も、終戦当時たまたま日本兵営が存在したために、ソ連軍に占領されたのであります(後略)」
■米国上院はソ連の領有権の確認を否定した。
◇サンフランシスコ講和条約の批准に当たって米国上院は、請求権を放棄した帰属先について、1952(昭和27)年3月20日、ソ連の領有権の確認を否定した。会議主催国の批准であるだけに、重要な意義を持つものである。
◇「決議。第82国会第2開期において上院は、1951年9月8日、サンフランシスコにて調印された対日平和条約の批准に、助言し且つ同意する。この助言と同意の一部として上院は、次の通り声明する。
この条約のいかなる規定も、ソ連邦の利益のために、南樺太及びこれに近接する島々、千島列島、歯舞諸島、色丹島における、またはこれらに対する日本国または連合国の条約に規定されている権利、権限及び権益並びに日本国が1941年12月7日に保有していた他の領土、権利、利益を減少させたり、害したりするものとみなされてはならない。
さらにこれらにおけるまたはこれらに対する権利、権限、利益をソ連に与えるものとみなされてはならない。
またこの条約のいかなる規定も、この条約の批准への上院の助言と同意も、1945年2月11日の日本国に関するヤルタ協定と呼ばれるものに含まれている諸規定を、ソ連邦の利益のために米国が承認することを意味するものではない(米国議会議事録から抜粋)」。

以上が本日のお話のあらましですが、ソ連の北海道進駐こそ米国の反対で実現しなかったものの、北方領土の島々が千島列島に含まれてソ連に領有されてしまったことが吉田茂全権の抗議でも覆らなかった経緯や事情が分かりました。米ソの駆け引きの中で、日本の固有の領土の占領が見過ごされてしまったことは、まことに残念です。
最後に受講者から寄せられたコメントをご紹介します。
「ソ連が参戦してきた経緯、そして終戦後のソ連の対応がよくわかりました。日本とソ連のクリール諸島に対する認識が根本的に異なっており、北方領土返還交渉は大変だなと改めて思いました」
「身近な課題であるのに、具体的な多くのことを知らずに生きてきた。改めて少しでもこの講座で分かったこと(が)あり、感謝です。北方領土問題、現状の日本とロシアを見ると、解決は無理なことわかる。事実にもとづいた話し合いができる環境を作らないと前に進まない。それにはずいぶん先のことになるのでしょうね」
「終戦が8月15日ということになっているが、今日の話を聞いて、簡単にそうとも言えないことが分かりました。しかも北方領土問題も複雑な駆け引きの下でそう簡単に解決できないもののようです。戦争するのも、終わらせるのも簡単ではないということです。だからといって、戦争は人間にとって避けられないものだと考えるのはおかしいと思います。先生の資料によって、この終戦時の動向がかなり見えてきた」