4月24日(木)、主催講座1「パレスチナを中心とした難民問題の実情」の第2回「ヨルダン川西岸等におけるパレスチナ社会の実情」を石狩市花川北コミュニティセンターで開催しました。講師は、北海道パレスチナ医療奉仕団・団長の猫塚 義夫さん、受講者は58名でした。
猫塚さんは「みなさんこんにちは。先週はガザ地区のお話をしましたが、今週はそれより東側のヨルダン川西岸のお話とどうしてこんなことが起きるのか、そしてどうしたら解決するのかについてお話していきたいと思います」と言って本日の講座を始められました。
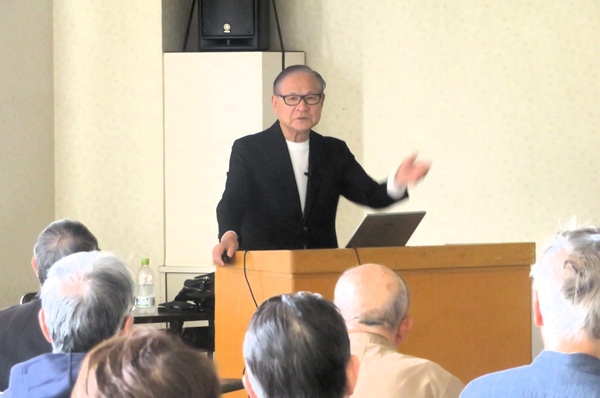
1.ヨルダン川西岸・東エルサレム
2024年10月7日以降・・
・入植者とイスラエル軍による「入植地」拡大と暴力が発生
虐殺508人(うち子ども124人)、逮捕・拘束9,000人,怪我人数千人。
・入植者の暴力:西岸北部ブルカで放火、西岸南マサフェル・ヤッタでオリーブ畑の破壊
・東エルサレム・ラマッカでは、表面上兵士は以前より少ない
・旧市街地の閉店、イスラエル国内での「反戦」行動
・ナブルスを囲んでいる検問体制
・ヨルダン渓谷とジェリコ方面の難民キャンプの閉鎖と軍事支配強化
全体的に入植者とイスラエル軍によりパレスチナが圧迫され、パレスチナ社会の沈痛化(もう一つの戦争、第2のガザ)が生じ、反撃の兆しも困難で、住民はおびえきっている状況。
2.パレスチナ「戦争しか知らない子どもたち」
・パレスチナの子どもたちがイスラエル軍法下にあるのに対してイスラエルの入植者はイスラエル市民法下にある
・子どもたち(16歳以下)の逮捕や拘留
投石など様々な理由によって起訴(密告すると不起訴に)されると軍法会議により公正な審理なしに投獄される。判決後60%の子どもはイスラエルの刑務所を転々とする。
なお、投石は、最大10~20年の刑罰。
毎年、約500~700人の子どもたちが逮捕・勾留されている。
この様な目に遭い、心が破壊された子どもたちがいる。
3.ヨルダン川西岸と東エルサレムのイスラエルによる軍事支配
・分離壁(高さ8m、延長650~700㎞)の存在と「入植地」建設の進行
※イスラエルは徴兵制(18歳で高校卒業後男性3年間、女性2年間)で、ほぼ全国民が軍務経験者。その制度の中で若者が何を学ぶか(パレスチナ人を打倒して国を守ることを徹底教育される)。
◇軍隊による市民・特に女性、子どもへの尋問の様子が紹介されました。
4.第16次パレスチナ医療・子ども支援活動
シェファット難民キャンプ 診療①(15名)
キリスト教区・老人保健施設 診療②(30名)
東エルサレムアラブ障碍者協会 診療③(40名)
国際障碍者デー 参加・紹介
オーガスタ・ヴィクトリア病院 視察・・パレスチナがん専門病院
ロシア正教・マリー協会 診療④(30名)
ラマラ近郊ウーレ村 障害児 診療⑤(60名)
ヒズマ村 診療⑥(40名)
ジェリコ 診療⑦(37名)
シェファット難民キャンプ 診療⑧(10名)
ジェリコ 診療⑨(25名)
ヒドウ村など 診療⑩(65名)・・計342名
◇シュファット難民キャンプやカルキリア、旧市街・キリスト教老人施設・SEED(猫塚さんと生年月日が全く同じ女性がいた)、バラータ難民キャンプなどでの診療の様子やオーガスト・ヴィクトリア病院視察の様子が紹介されました。
◇「赤い涙」運動
東京で始まった「パレスチナに涙を。」運動は全国に広がったが、札幌や鹿児島では、赤い涙を描くことでアクションを起こし続けている。2024年6月9日、札幌と鹿児島の赤い涙をシェファット難民キャンプへ贈呈、岩手県の小中学校からのメッセージをアラビア語に直したメッセージボードとして届けた。
◇NHKの取材
北海道医療奉仕団の診療の様子を1月にNHKが取材してくれた(NHK単独取材は許可されなかった)。
◇子ども支援活動
現地の人たちに溶け込むには、子どもたちと仲良くなるのが一番だが、その中で子どもたちの気持ちが荒んで、穏やかに話ができなくなっているのを感じる。それを和らげるのに学校教師の協力を得て、バレーボールを取り入れ、子どもたちは大変喜んでくれた。
現地の授業は、主要5科目だけ。
◇カランディア検問所
イスラエルは、検査に従う東エルサレム住民とイスラエル入国許可証を持っているパレスチナ人以外の検問所の通過を禁じている。
◇医療奉仕団員や仏・議員団の入国禁止
昨年、パレスチナを助ける行動をしたとして奉仕団の女性医師と教師が5年間のイスラエルへの入国拒否とされ、日本へ強制送還された。また、フランスがパレスチナの国家承認を表明したことにより国会議員団は入国拒否、外交官が拘束された。
5.パレスチナ・イスラエル問題の今日の状況とその意味
・極右政権・「臨時内閣」は崩壊しかかっている
世論は、即時停戦か停戦して人質を戻せという意見が72%超で、デモも興っている。
・入植者(新移民)の凶暴化とアウトポスト(非公認入植地)も拡大
ガザでのジェノサイド侵攻を維持しつつ、北部戦線(レバノン・ヒズボラ)へ兵力を移動(戦争挙国一致国家)。
◇他にも難民はいるのに、奉仕団はどうしてパレスチナに取り組むのか?
・パレスチナに入国するにはイスラエルの許可が必要であり、こんな不都合で矛盾したことは他国では無いから。また、16年間に及ぶガザ地区の封鎖(世界最大の天井のない監獄)のもとでの生活は、現在の世界で人権侵害の最たるものである。
・世界的位置付け:歴史の逆流への命と生活を賭してのパレスチナ人の闘いが意味深いものであるから
◇「平和国家」日本からの取り組みの意義:世論・国際法・平和憲法での解決を
日本からの奉仕団は大変歓迎され、また来て欲しいと言われる。
パレスチナの人々は外の世界に求める気持ちが強く、自分たちを信じてくれる人たちを大事にしていることを痛切に感じる。
6.今後の情勢
・レバノン・シリアへの軍事侵攻:大ユダヤ主義の根底にはさらに拡大する考えがある
・医療国際NGOの入国制限や拒否
・国連など国際社会への非協力
7.ガザ軍事侵攻「ガラスの停戦合意」と西岸攻撃
赤い涙運動の仲間で常に勉強会を行っている。
・「停戦合意」1月19日~3月1日⇒3月18日ガザ全面奇襲軍事攻撃で900名を超える虐殺
極右勢力への配慮でネタニアフ内閣維持、ガザ支配の有利な条件づくり。
・長いスパーン(5年~7年)での停戦の考え方も出てきている
・「赤新月(赤十字)」の車両が襲撃され、イスラエルは誤爆と発表したが、あきらかに故意によるもの
8.No Other Land(故郷は他にない)
アメリカのドキュメンタリー映画。第97回アカデミー賞・長編ドキュメンタリー賞 受賞。
札幌は、シアターキノで上映。ただし、イスラエルは無論のこと、アメリカでも上映禁止となっている。
9.ユダヤ・シオニストの「遠大」な計画
ベン・グリオン運河計画(ベン・グリオンはイスラエル共和国初代首相兼国防相)
スエズ運河に代わる運河をイスラエルに!
10.UNRWAの活動禁止と米大統領選トランプ再選
・UNRWA(国連パレスチナ難民救済事業機関)活動禁止
医療・教育・福祉の崩壊・・1月30日~。
パレスチナ人の生活と人権の破壊⇒ガザ軍事侵攻に続く、第2のパレスチナ攻撃(難民キャンプ診療所・小中学校閉鎖、医療崩壊)。
子どもたちの破壊⇒社会精神的問題へ・・。
・トランプ米大統領再選―親イスラエル政権の誕生:100%イスラエルを支持
米軍事産業潤沢化。在イスラエル米大使館のエルサレム移転・首都認定(2018)。UNRWへの供出金凍結。ゴラン高原の入植地を「トランプ高原」と命名(2019)。
※ケネディ大統領は政教分離策をとったが、レーガン大統領はそれを結び付けて福音派を取り込んだ(NHKバタフライエフェクト)
11. 札幌市議会への意見書採択要求(2025年1月24日)
◇意見書―陳情団体「パレスチナに平和を求める市民連合」(北海道パレスチナ医療奉仕団、戦争をさせない市民の風・北海道、赤い涙)
1)6週間の一時的停戦合意の完全履行と恒久的停戦への伸展を求める
2)UNRWAのイスラエルでの活動禁止の国会決議を撤回しパレスチナ難民への支援の保証を求める
3)今後、武力による現状変更を禁じる国際法を遵守し平和外交の推進を求める
4)以上を札幌市議会の意見書として日本政府がイスラエルなど国際社会に訴え行動するよう働きかけることを求める
◇決議案第1号
意見書におおむね基づく内容で、政府にパレスチナにおける平和な暮らしが一刻も早く実現するよう強く求める決議案が採択された。
※「パレスチナに平和を求める市民連合」の要求は、すべての関係先に提出する意見書採択であったが、内閣総理大臣・外務大臣と全議員への2か所のみの提出となる決議書採択という結果となって完全に満足できるものではなかった。しかし一歩前進ではあり、今後も働きかけていきたい。
12.医療・子ども支援で感じたこと
◇生きながら殺されているのがガザの人
1)民主主義と人権を守る「世界の最前線」である
①生命と人生を賭して、「自分達の土地」のための闘いである
②世代を継承し、生活に根ざした闘いである
2)「医療・子ども支援活動」の継続と発展
3)現地との信頼関係の構築と発展
◇医療奉仕団の使命
人権と人間の命・健康・尊厳を守り増進させること。
・「医療奉仕団」とは、憲法前文・平和的生存権に基づく、非武装・非暴力による民衆のための国際NGO組織でbeyond the border(国境などは飛び越える)をモットーとする
※毎年行われている健康増進国際学会において、近年では演題内容への介入が起きつつある。
13.公的年金積立金の投資
公的年金積立金がイスラエル軍需に投資されている。
・イスラエル軍への兵器供給会社へ40億円
・イスラエル国債・・2270億円出資
14.中島優子先生(国境なき医師団・日本会長)講演
2024年6月。3日間で1,000人参加。
猫塚さんは、お終いに5月17日に北海道自治労会館で行われる「ナクバ(大厄災)の日」北海道in2025講演会(講師:岡真理氏、平山裕人氏)を案内して、本日の講座を終えられました。

戦争しか知らない子どもたちや生きながら殺されているといわれるパレスチナの人々の痛ましい状況が大変良く分かるお話でした。
最後に受講者から寄せられたコメントをいくつかご紹介します。
「人間の命、人権、健康、尊厳を守り増進させる医療奉仕団に頭が下がります。今回、こんな講座ができたことに大変うれしく頼もしく思います。ありがとうございました」
「パレスチナの現状、恐怖で胸が苦しくなる状況。人間ではない行動。戦争しか知らない子供たち。人を殺し殺される体験をしなければならない軍事支配の国のある現実を猫塚先生の生命をかけた行動により具体的に直接話して頂いた事に感謝し、敬服しています。『人間の生命と尊厳を守る』との活動に!!」
「命懸けの活動、大変尊敬いたしております。どうぞお体に気をつけて下さい。現代の重大問題について、核心に近づく努力をすることの大切さを再認しました」
「特に印象に残ったのは、イスラエル兵の実情とパレスチナ人の状況です。イスラエル兵も『国を守る』ために軍隊に入っていかに将来設計に生かすかということで闘いを強いられている。そしてパレスチナの置かれた状況も一筋縄ではいかない。歴史的しがらみで解決が容易でない。まだまだ時間はかかると思うが日本の果たす役割も大きいと思う」
「ガザの実態に言葉もない。戦争しか知らない子供たちをつくってはいけない」